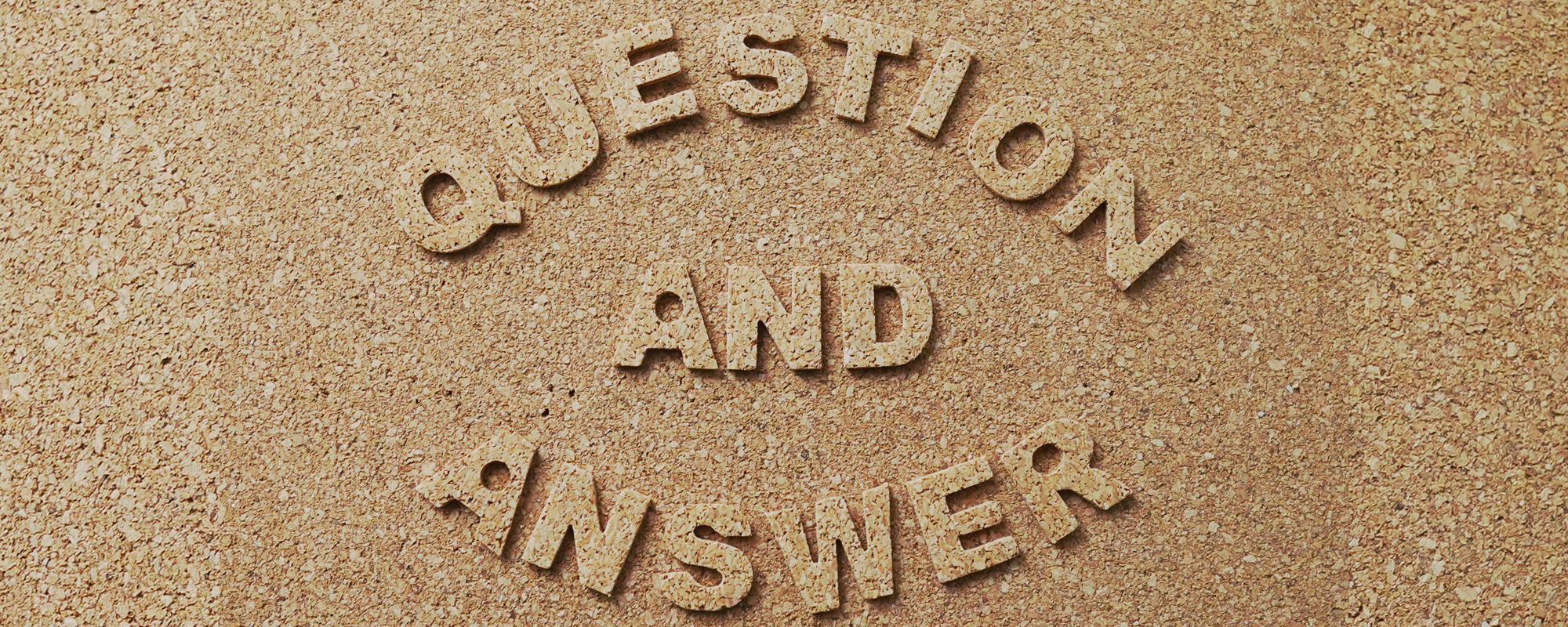
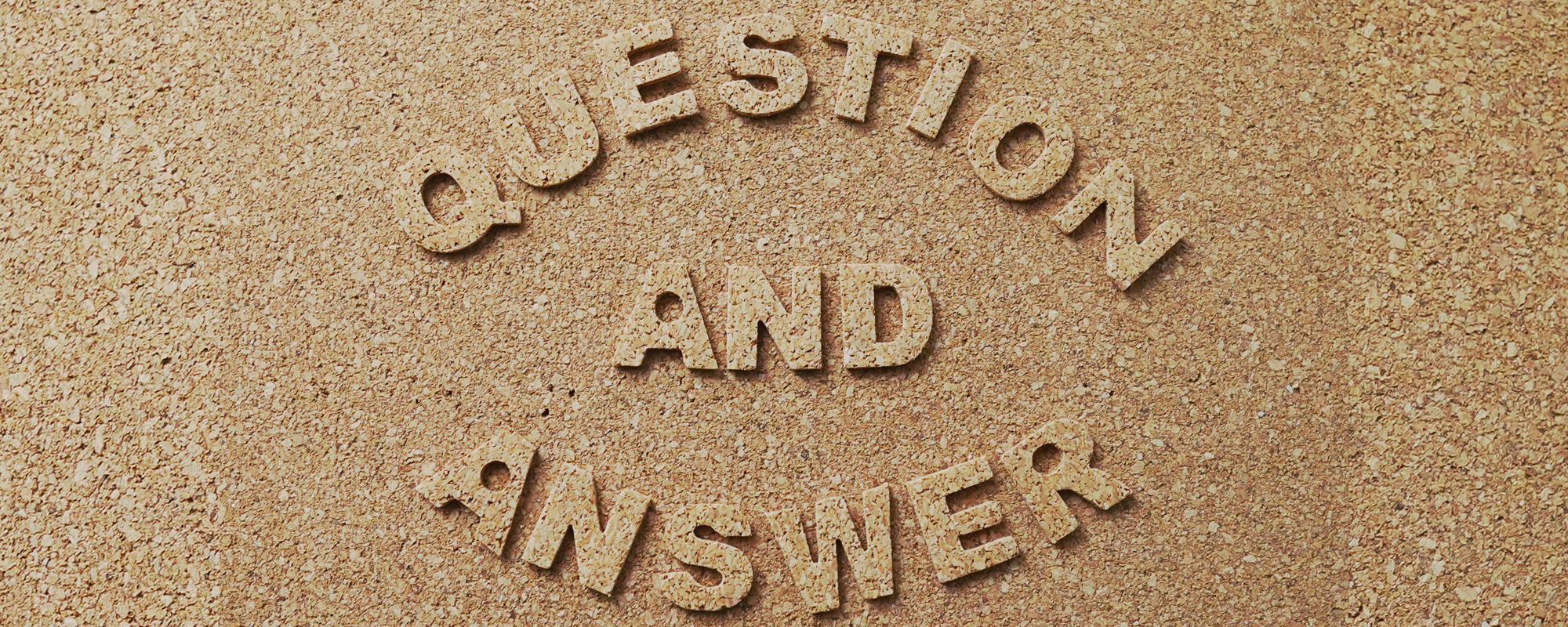
トップ > Q&A
よく頂く質問
- 料金はいつから発生しますか?
- 料金は派遣就業開始後からしか発生しません!
なお、料金は実働時間×単価で決まります。詳しくはお問い合わせ・ご相談ください。 - 依頼の時は何を伝えればいいですか?
- 必要な人材の人物像、スキル、条件などをお伝えいただけると、以後の対応がスムーズになります。要件が固まっていない場合でも、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
- 見積だけ出してもらうことはできますか?
- もちろんお見積りだけのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
- 月末月初や週3~4日の派遣を依頼することはできますか?
- はい、可能です。
特定の時期や、特定の曜日・時間帯など、業務の繁閑に合わせて必要な時期だけご利用いただけます。
ご契約期間によっては対応可能な業務やスタッフに制限がある場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 - 1日や1週間など短期間の派遣を依頼することはできますか?
- ご契約期間が30日以内の「日雇派遣」は、法律の定めによって原則禁止されています。
例外として「日雇派遣」が認められるのは、政令第4条1項で定める業務に派遣する場合、もしくは以下いずれかに該当する人を派遣する場合です。
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
・主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上) - 人材派遣はどのような料金形態ですか?
- 派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生しません。
就業開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。契約によって、派遣労働者の通勤関連の費用分などを派遣料金とは別にご請求する場合があります。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。 - 派遣スタッフの通勤交通費は、どのような取り扱いになりますか?
- 派遣スタッフの通勤にかかる費用は、派遣先にご負担をお願いしています。
- 人材派遣の対応エリアに制限はありますか?
- 原則東海地方を対象にお取引させていただいておりますが、お客様とのお話し合いによっては、エリア外への人材派遣も検討させていただきます。
- 派遣で対応できない職種や業務はありますか?
- 法律の定めによって、一部の業務について派遣が禁止されています。
禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。 - 派遣の受け入れ期間に制限はありますか?
- 人材派遣においてはすべての業務に対して、次の2種類の制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
(2)派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
以下の「人」と「業務」は、期間制限の例外対象として(1)(2)いずれの制限の適用も受けません。
例外対象の「人」
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者(無期雇用派遣労働者)
・60歳以上の派遣労働者
例外対象の「業務」
・日数限定業務
・有期プロジェクト業務
・産前産後/育児休業・介護休業代替業務
3年の制限なく同一の派遣スタッフが就業継続できる例外として、「無期雇用派遣」があります。 - 派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いを依頼することは可能ですか?
- 派遣スタッフが金銭や有価証券などを取り扱うことについて、特に法律上での定めはありません。
パーソルテンプスタッフでは、派遣スタッフが行う業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。
業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと必要最小限の範囲において対応します。
なお、派遣スタッフに出張をさせる場合や、車両(社有車など)を業務に使用するために運転させる場合なども、別途覚書を締結の上で対応します。 - 派遣契約の際に必要なものは何がありますか?
- 派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の選任が必要です。また、労働者派遣基本契約と労働者派遣契約(個別契約)の2種類の契約を締結する必要があります。
指揮命令者と派遣先責任者
指揮命令者と派遣先責任者の役割などは以下のとおりです。
これらは兼務することも可能ですが、役割の違いを考慮したうえで、それぞれ適切に選任することが大切です。
<指揮命令者>
役割: 派遣スタッフへの業務指示
選任対象: 派遣スタッフに対し、直接業務を指示する立場にある方
<派遣先責任者>
役割: 派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応などの窓口
選任対象: 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
選任条件: 派遣先事業所ごとに派遣スタッフ100人につき1人以上
※派遣先が雇用する社員の数と事業所における派遣スタッフの数の合計が5人以下の場合は選任不要とされています。
労働者派遣基本契約と労働者派遣契約
労働者派遣基本契約と労働者派遣契約(個別契約)のそれぞれの内容は、以下のとおりです
。
<労働者派遣基本契約>
労働者派遣法上の締結義務はありませんが、派遣先と派遣元間における取引上の基本事項を定める重要な契約であるため、両者間で締結する場合がほとんどです。弊社では、初回の人材派遣ご利用時に必ず締結をお願いしています。
労働者派遣基本契約の主な記載事項
派遣料金の支払条件、労働者派遣法その他関係諸法令の遵守、契約の解除、派遣労働者の個人情報保護、機密保持などについて記載します。
<労働者派遣契約>
労働者派遣法上、締結が義務づけられており「個別契約」とも呼ばれます。また、契約に定めなければならない事項が決められており、必ず契約に記載する必要があります。(法定記載事項)
労働者派遣契約の主な記載事項
個別の派遣契約ごとに定めるべき派遣期間、派遣就業をする日、就業場所、業務内容、派遣人数などを記載します。 - 派遣スタッフの受け入れにはどのような準備が必要ですか?
- 派遣スタッフの受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣スタッフが就業初日に持参すべきものがあれば、事前に派遣元にお伝えください。
事前にご準備いただく事項の例
(1)受け入れに関する社内周知
・派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明
・契約期間、勤務する曜日や時間
(2)指揮命令系統の明確化
(3)社内手続き
・入館証やIDカードの発行
・社内ネットワーク等の利用手続き
(4)業務上必要な機器・備品・マニュアル等の準備
・デスクや事務用品、パソコン機器等の準備
・業務上必要なアプリケーションのセットアップ
・業務マニュアルや引継ぎ書の準備
また就業開始初日には、下記のような案内・説明をしていただくと、派遣スタッフは安心して就業することができます。
初日にご案内いただきたい事項の例
(1)関係者への紹介
・派遣先責任者および指揮命令者
・就業部署の方々や業務上で関わる部署
(2)社内設備・フロアの案内
・コピー機やFAXの場所、使い方
・備品の保管場所
(3)社内ルールの共有
・入退室に関するルール
・オフィス内やデスクでの飲食・喫煙ルール
・機密情報の取扱いルール
(4)業務に関する概要の説明
・業務全体の流れ、担当する業務内容とその役割
・会社独自のシステムの概要と使用方法
(5)座席表・組織図などの配布 - 交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?
- 労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。
そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。 - 派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか?
- 業務上必要な場合は、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の管理監督責任のもと契約業務内容の範囲で対応しています。
- 派遣先の都合で、派遣スタッフに急な休みを取ってもらうことは可能ですか?
- 派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
会社が独自に定める休日(夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日など)がある場合は、派遣のご依頼時に派遣元にお伝えください。 - 契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
- 派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。期間満了のタイミングでの雇用をご検討ください。三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で派遣契約を終了し、紹介予定派遣契約を新たに締結することは可能です。
- 派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらうことは可能ですか?
- 派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨をお伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、対応可能な派遣スタッフを人選します。 - 派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか?
- 派遣スタッフの安定就業のため、以下事項への配慮をお願いいたします。
(1)仕事の指示、業務に関する情報共有
・業務の指示は、派遣契約で定めた範囲内で行ってください。
(契約内容に修正が必要な場合は派遣元にご相談ください)
・業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じように直接派遣スタッフにご指摘ください。
・派遣スタッフにも業務に関連する情報をお伝えいただくと、業務に対する理解が深まります。
(2)就業環境への配慮 ・職場におけるハラスメント*防止措置義務に関する規定は、派遣先にも適用されます。社員と同様に派遣スタッフにも必要な措置を実施し、適切に対処ください。
*セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタニティハラスメント)、パワーハラスメント
・派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。
(3)コミュニケーション
・「派遣さん」などの呼び方ではなく、個人名でお呼びください。
・定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができます。また派遣スタッフからも相談がしやすく、安定就業につながります。
・業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加・不参加は、派遣スタッフの判断によります。参加を強制することはできません
(4)福利厚生施設利用の配慮
派遣先の労働者が利用する福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室についいては、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。
(5)教育訓練、能力開発
派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じて、当該訓練を実施する等の必要な措置を講じなければなりません。ただし、既に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練実施が可能である場合を除きます。
